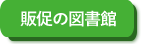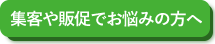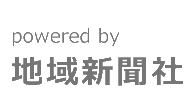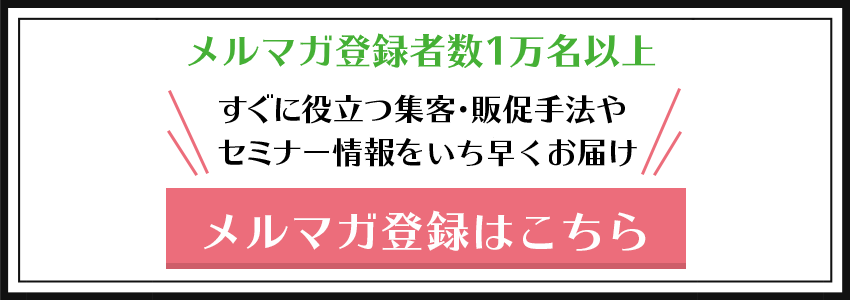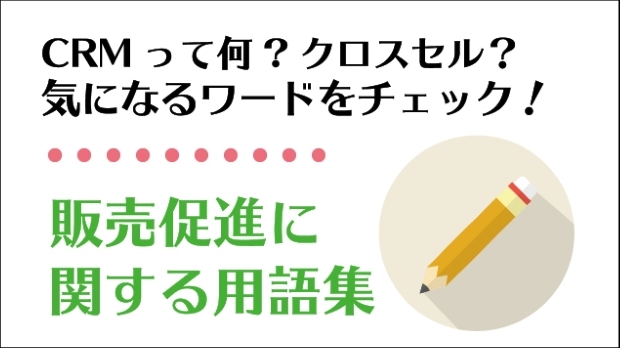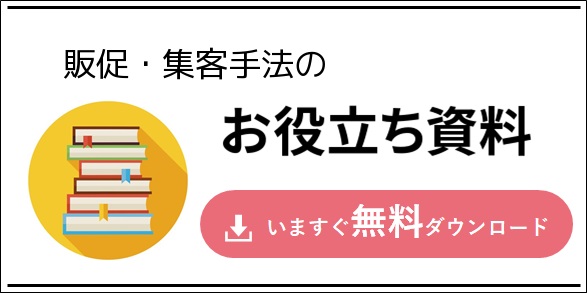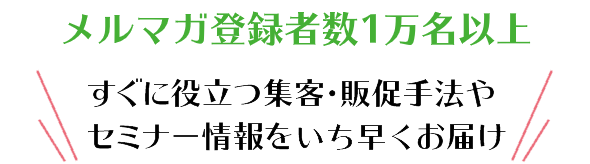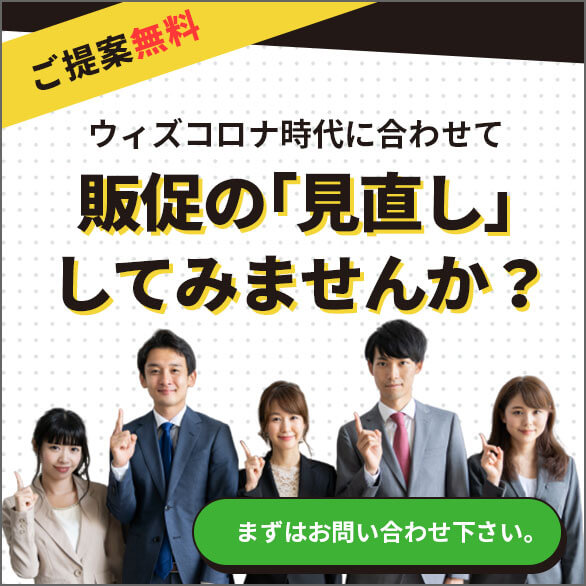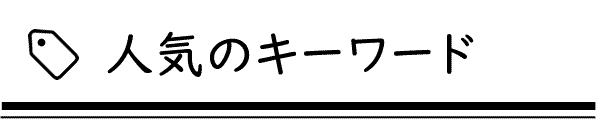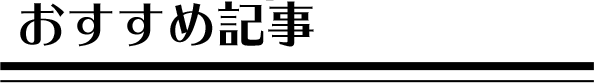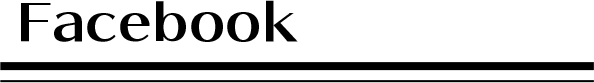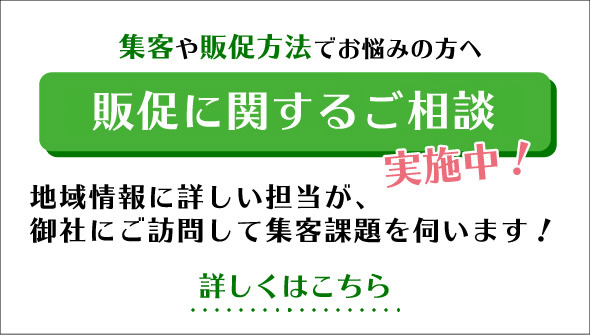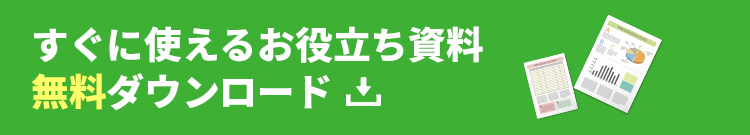メールマガジンを発行することに興味をお持ちのあなたに!
前回記事「メールマーケティングのススメ」で「メルマガ」についてご説明しました。
今回は、メールマガジン(メルマガ)を始める前に事前準備としてやっておきたいことを中心にお伝えします。
インターネット上の発信媒体であるメディアには、マーケティング的にいうと、「待ち」のメディアと「攻め」のメディアがあります。
「待ち」のメディアとは、ウェブサイトやブログ、TwitterやFacebookなど、自分の発信を見てもらえるかどうかは相手任せのメディアです。
メルマガは「待ち」のメディアとは根本的に異なり、発信者側が情報を直接届けられる、インターネット上では「攻め」のマーケティングができる数少ないメディアのひとつです。
メルマガの目的、担当者、テーマなどを決める
基本事項をメルマガ配信前にしっかり決めておくことで、配信後の効果が違ってきます。
継続的かつ良質なメルマガ発行にもつながります。
1. 目的
なにを実現するメルマガなのかを、はじめにしっかり決めておくことが重要です。
メルマガで実現できることはたくさんあります。
・売り上げを伸ばす
・顧客との関係を維持する
・顧客をフォローする
・顧客を教育する
・求人募集
・ブランディング
どれを目的とするのか、また自社のビジネスモデルのどこにメルマガを活用するのかを決めましょう。
2.対象
自分の発行するメルマガは、誰が対象なのかを明確にします。
名刺交換をした人なのか、ウェブサイトから登録をした人なのか。また、どの事業に興味を持っているのか。
それによって配信する内容にも違いが生まれます。
3.テーマ
自分の発行するメルマガに何を書くか。
お客様が求めている情報を理解し、お客様の役に立つ情報を届けましょう。
売りたい商品に直結する情報よりも、その周辺情報の配信が喜ばれます。
具体的には、求人広告を売りたいならば、雇用情勢や内定率などの情報ならば喜んで読まれます。
4.担当者
発行するメルマガは誰が書くのか。
社内のことを理解し、ブランディングなどを意識しながら継続的に書ける人間を選びましょう。
5.タイミング
いつメルマガを配信するのか。
会社員の方に通勤途中に読んでもらいたいなら、通勤時間帯に送るのがよいでしょう。
仕事のスタート時に読んで欲しいなら、9時少し前がベストでしょう。
このようにメルマガ読者の行動を予測しながら、配信タイミングを検討しましょう。
6.周期
メルマガの配信頻度。
配信頻度が高くなるとスパムメールだと思われます。
効果が最大化される適切な回数を考えましょう。
7.システムの選択
どの配信システムを使って配信するか
配信システムの乗り換えには手間がかかります。
メルマガにあったらいい機能をきちんと検討した上でシステムを選定しましょう。
メルマガをビジネスで発行するときに、こだわるべきポイント
メルマガをビジネスで発行するなら、こだわるべきポイントは「知られていないメルマガは、存在していないのと同じ」ということです。
発行者がいくら愛情をそそいでも、いくら業界ナンバーワンの人が書くメルマガであっても、それだけでは意味が無いのです。
認知されていないものは読むことができませんし、ましてやその先の商品購入までたどり着きません。
「認知→登録」という流れ
知られていないとメルマガの存在価値が伝わりません。
厳密にいうと、次のようなことになります。
・知っている人には、メルマガの価値は伝わります
・知らない人には、メルマガは存在していないのと同じ
発行者はメルマガを書くことにより、メルマガ読者の口コミで認知が広がるイメージを持っているかもしれませんが、それは幻想に近いです。
内容の良さで自然に読者が増えるメルマガは、ほぼありえないでしょう。
これは断言できます。
一般のメルマガはどうやって読者を増やしているのか?
それでは、一般のメルマガはどうやって読者を増やしているのでしょう?
答えは「告知の努力」。
認知をしてもらう努力を日々繰り返しています。とくに告知の分散をしています。
1.名刺にメルマガのタイトルを印刷する
2.ウェブサイトの目立つ位置にメルマガの情報を掲載する
3.他の社員にもメルマガの宣伝をしてもらう
4.書籍から特設ページに誘導(レポートプレゼント)する流れを作る
5.セミナーや講演で紹介する
6.Twitterで新着情報を公開する
7.Facebookのプロフィールに書く
毎回このような泥臭いような紹介を繰り返しながら、やっと微増するのが現実。
成功しているメルマガ発行者は、基本に忠実
成功しているメルマガ発行者は、認知してもらうことに力を注いでいます。
メルマガは、人によっては有益なコンテンツに映るかもしれません。
しかし、そう思わない人もいるのが事実です。
そのために読者の循環が必要です。
「読者が固定化する人数 > 解除する人数」となるように、有益なコンテンツを出し続けることがポイントです。
使えるメルマガ、メルマガの有効性を考えるときには、まずはメルマガの存在を知ってもらうこと= 「入り口」を考えてみてください。
まとめ
・メルマガをはじめる前にメルマガの目的、担当者、テーマなどを決める
・メルマガは告知の努力をして読者を増やす
・成功しているメルマガ発行者は、基本に忠実に認知してもらうことに力を注いでいる