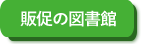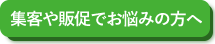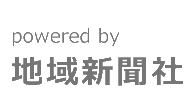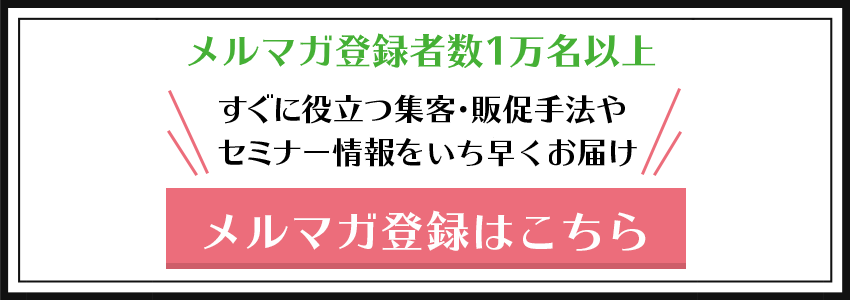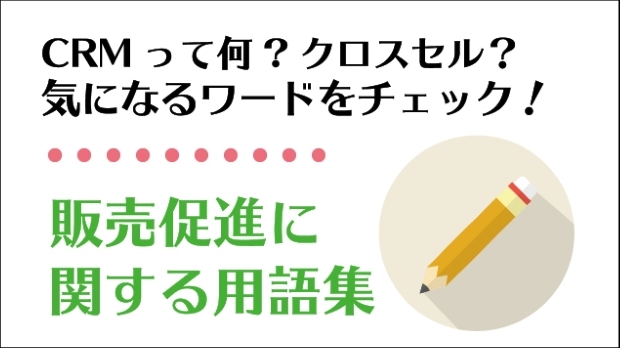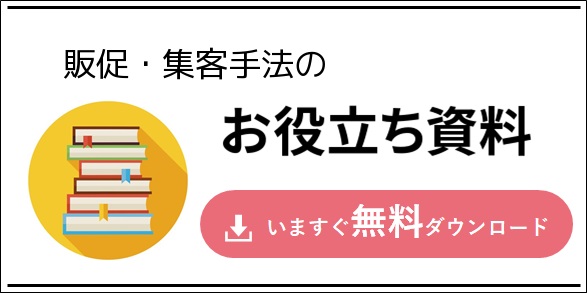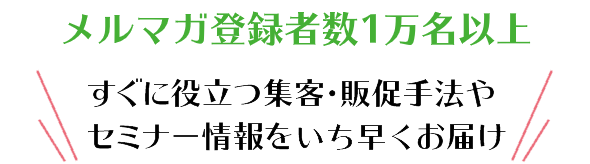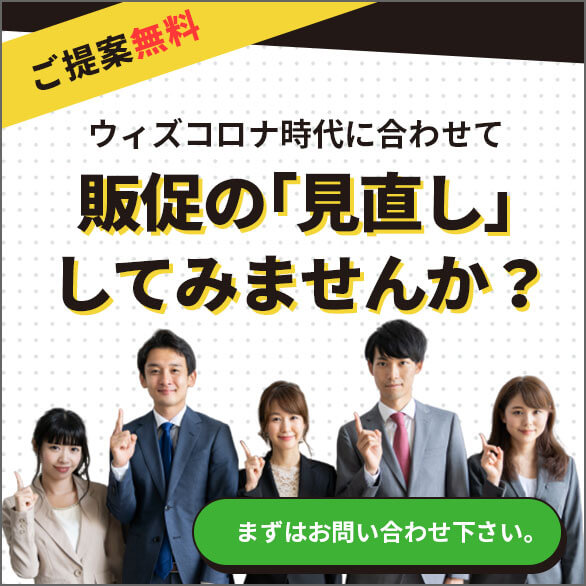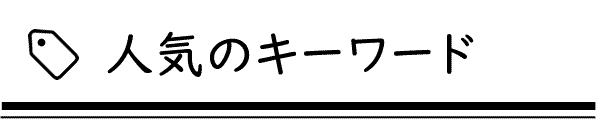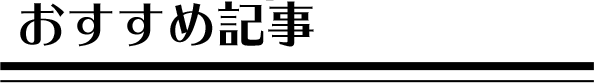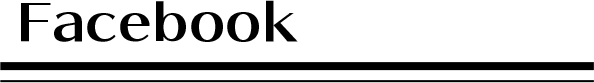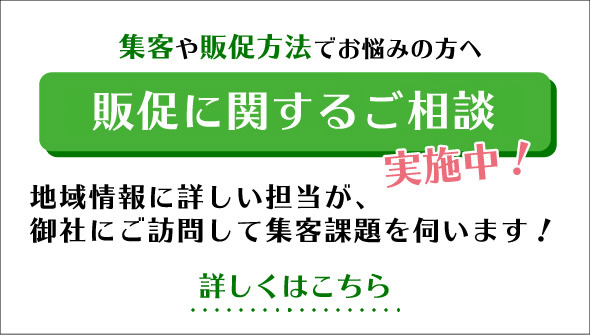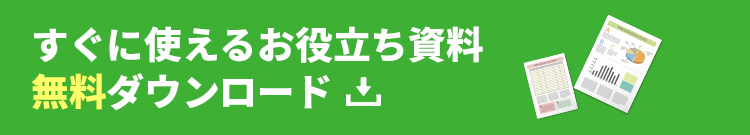私(筆者)は広告審査の仕事を担当業務として行っています。規制に則り広告審査を行う意義は、広告読者・消費者を虚偽・誇大・詐欺広告による被害から守ることにあります。では、その被害は実際にどれくらいのものになるのでしょうか?広告審査・広告規制の重要性を再確認することになりました。
【目次】
1.規制に反する広告による被害額は?
2.規制の強化だけでなくリテラシー向上による被害防止
1.規制に反する広告による被害額は?
消費者庁は2013年時点での悪質商法や誇大広告による消費者被害額の推計値を公表しており、その支払われた被害額は約5兆7千億円。これは当時の国内総生産(GDP)の約1%に相当する額ということです。
また2018年6月28日に発表された消費者庁「2017 年消費者被害・トラブル額の推計結果について」を見ると、広告規制に反する虚偽・誇大・詐欺広告による消費者被害の程度をうかがうことができます。ここで言う「消費者被害・トラブル」の捉え方は回答者によって異なり、誤差を含む数字であることには注意すべきですが、2017年の被害額(※)は約4.9兆円にもなります。
※「既支払額(信用供与を含む。)」であり、実際に消費者が事業者に支払った金額にクレジットカード等による将来の支払を加えたもの。
正直、想像をはるかに上回る金額ですね。
もちろん、規制に則った広告審査がより厳格に行われてさえいれば上記のような何兆円もの被害額は出なかった…と断定することはできません。現実的に限界はあります。しかし、広告審査の十分な浸透や消費者マインドの向上が図れていれば……これは全くの感覚値ですが何千億円ものお金が「被害額」という悲しい形で生まれることはなかったのではないかと思います。
こうして考えると、広告審査というのは決して華やかな仕事ではないかもしれませんが、社会経済にとても大きな影響を与える仕事だとも思えるのです。
2.規制の強化だけでなくリテラシー向上による被害防止
上記の莫大な被害額を見て感じるのは、規制をする側・広告審査をする側の不断の努力は不可欠ですが、広告読者・消費者一人ひとりのリテラシーの向上も目指す必要があるということです。
景品表示法・薬機法・健康増進法など、消費者を守るための法令・規制があることを知っていただき、クーリングオフの活用を奨励するなど、取り組み方はたくさんあるはずです。日本広告審査機構(JARO)は、広告に対する消費者からの意見や相談を電話やメールで受け付けており、また消費者向けセミナーも開催しています。消費生活センターでは、広告表示や商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどの消費者からの相談を専門の相談員が受け付け公正な立場で処理に当たっています。
残念ながら、規制に反した広告やその被害はなかなか減っていないのが現状かもしれませんが、規制をする側・広告審査をする側と広告読者・消費者一人ひとりの意識の向上が消費者被害を減らす決め手となることは間違いありません。