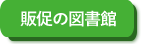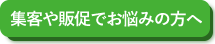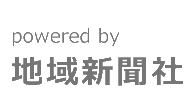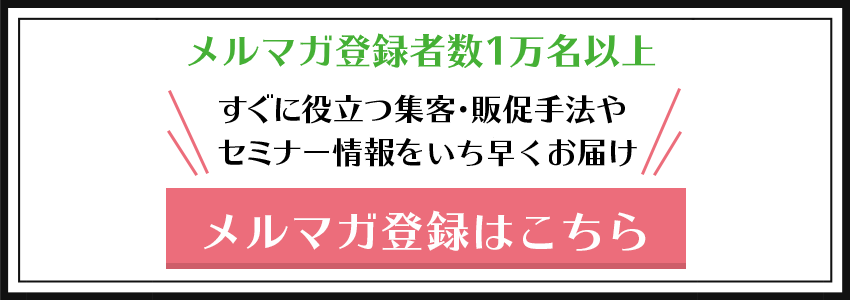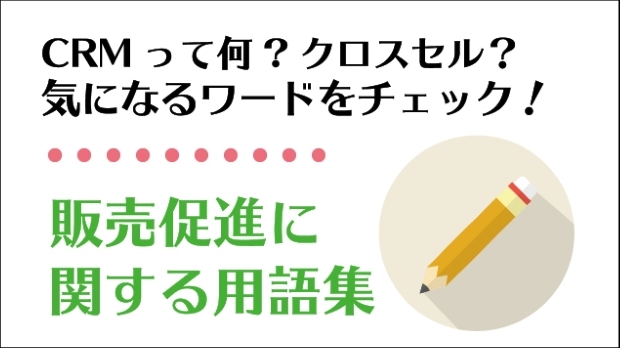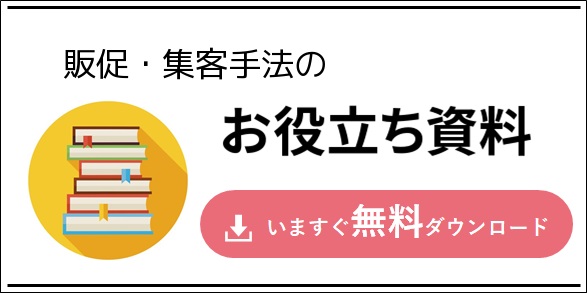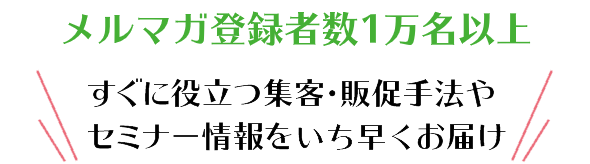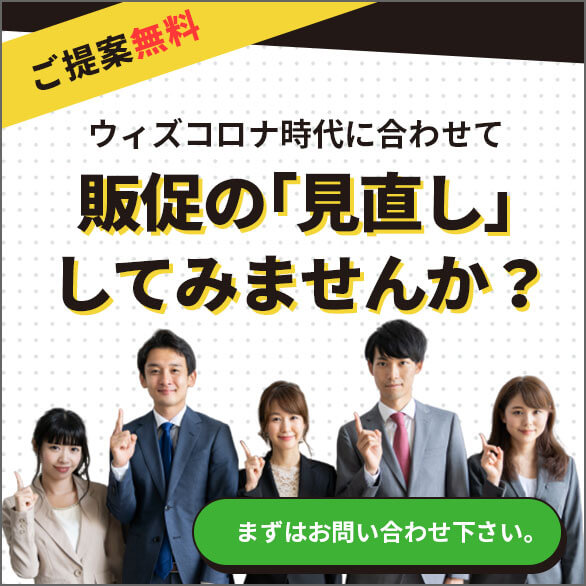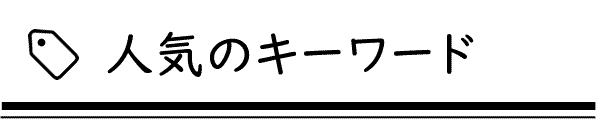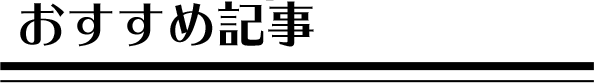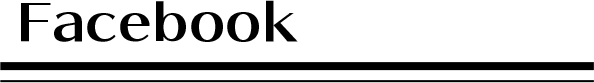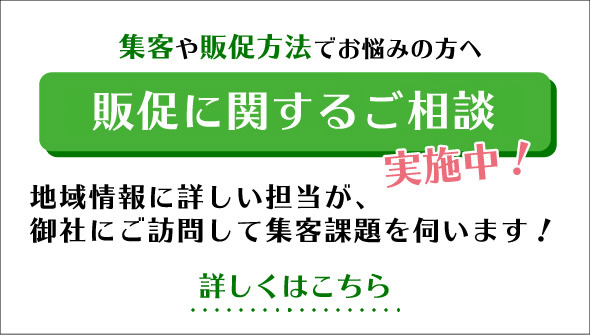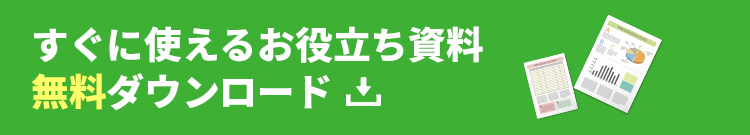二重価格表示のルールと正しい広告の書き方事例

販促の大学では以前より広告マーケティングにおける法令遵守(コンプライアンス)の情報として、景品表示法などの解説をしてきました。
今回から、実際に行政処分(措置命令)を受けた法令違反事例をもとに、リスクの高い広告表現を示し、受け手と長期的な信頼関係を結べる広告マーケティングのお手伝いをいたします!
【目次】
1.実例をもとにした二重価格表示の違反ケース
2.二重価格表示におけるルール
1.実例をもとにした二重価格表示の違反ケース
ある量販店の新聞折込チラシの掲載内容について、不当な二重価格表示を行っているとして、消費者庁が景品表示法の措置命令を出しました。
これは、量販店のセール企画の新聞折込チラシに処分が出されたものですが、
(当)10,000円→特別価格!レジにて5,000円
といった価格表示をしており、
同じくチラシ内に
(当)は当店平常価格です
と但し書きを記載していましたが、
実際は、(当)と称する金額は店舗において最近相当期間にわたって提供された実績のないものであり、販売実績のない二重価格による、景品表示法の有利誤認表示とみなされ、措置命令が出されたのです。
2.二重価格表示におけるルール
広告に二重価格表示をする際の注意点を挙げます。
(1)次のような場合は不当な二重価格表示に該当するおそれがあります。
●同一ではない商品の価格を比較対照にして表示を行う場合
●比較対照にする価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合
(2)過去の販売価格を比較対照とする二重価格表示について
●同一の商品で「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。
●同一の商品で「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照とする場合には、その価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどを正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。
今回ご紹介した実例は、この点で不当表示であると判断されました。
(3)将来の販売価格を比較対照とする二重価格表示
将来の販売価格が実際に販売することのない価格であったり、ごく短期間のみで販売するにすぎないなど、根拠が不十分であるときは、不当表示に該当するおそれがあります。
(4)希望小売価格を比較対照とする二重価格表示について
あらかじめ公表されているとはいえない価格を希望小売価格として比較対照価格にする場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
(5)競争事業者の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
●消費者が代替的に購入できる最近の販売価格とはいえない価格を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
●一般市場で売買される普通の値段を比較対照価格とする二重価格表示については、相当数の競争事業者の実際の販売価格を正確に調査することなく表示する場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
価格表示は広告において最も読者の目に触れる箇所です。だからこそ、読者をあざむくような表示を行えば信頼を瞬時に失い、行政からも責任を問われる結果となりやすい部分なのです。充分に注意を払った表示を心掛けてください。
まとめ