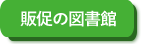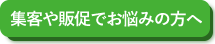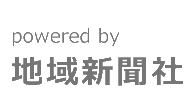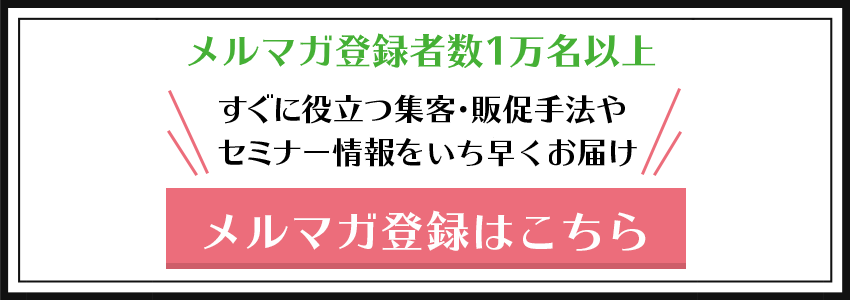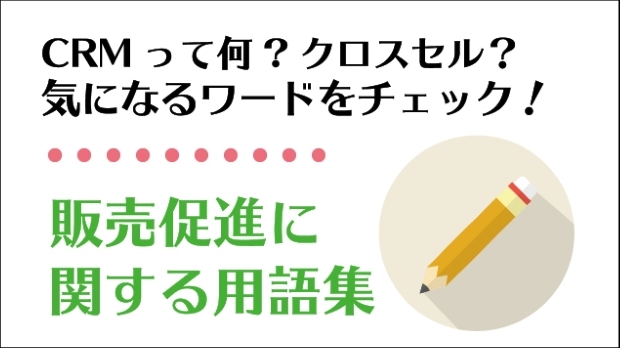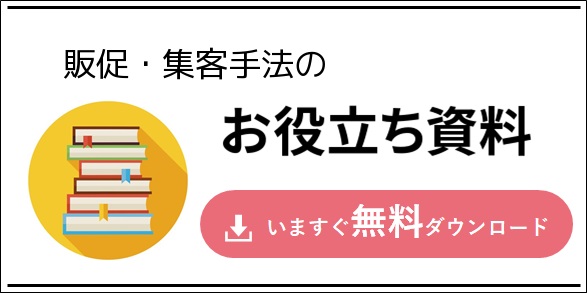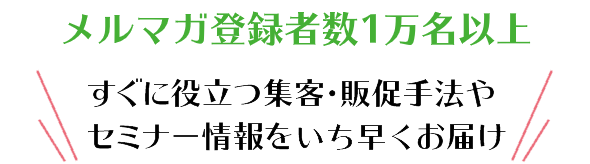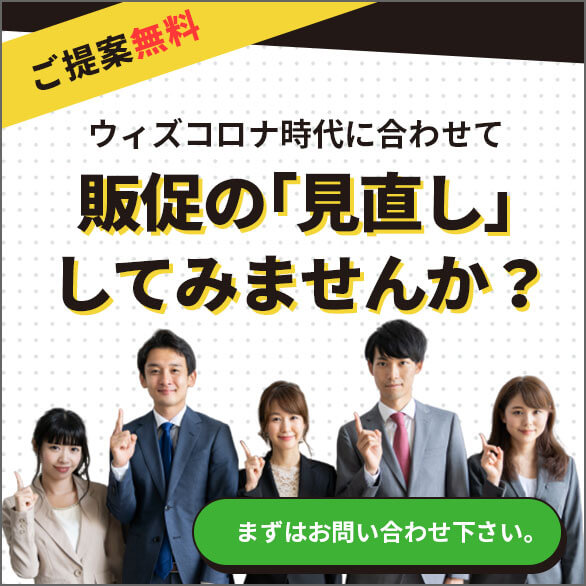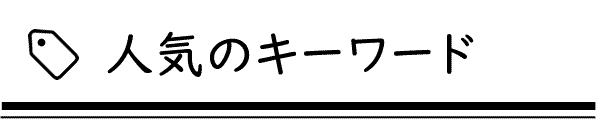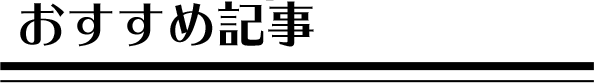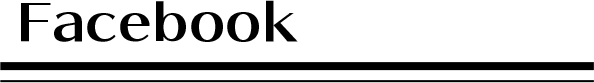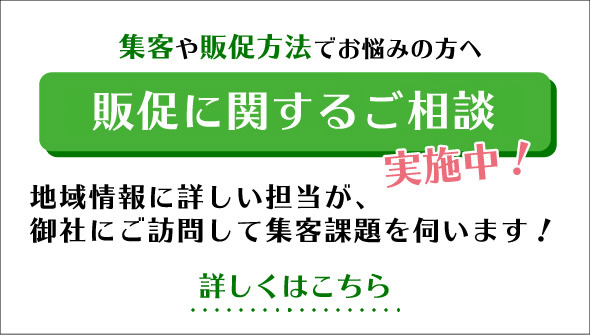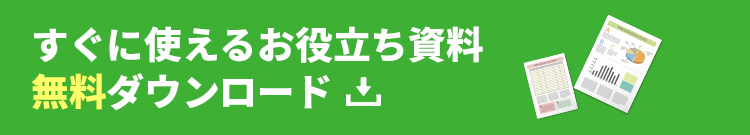求人広告における労働時間・休憩・休日や手当の法律上の定義と書き方

求人広告を考える上で気をつけたい「労働時間」。
「休憩」「休日」などは労働基準法でしっかりと定められています。
それらをきちんと理解して、正しい求人広告を作りましょう。
【目次】
1.「労働基準法」で定められた定義とは?
2.時間外手当などが必要なケースとは?
1.「労働基準法」で定められた定義とは?
労働基準法では、以下のように定義しています。
●労働時間(法定労働時間)
休憩時間を除いた実労働時間のこと。
原則、「1日に8時間」「1週間に40時間」を超えて働かせてはならない。
●休憩
労働時間が「6時間を超える場合は45分以上の休憩」「8時間を超える場合は1時間以上の休憩」を与えなければいけない。
※6時間以内の労働の場合、休憩時間を定める規則はない
●休日(法定休日)
最低でも「毎週1日の休日」または「4週間に4回以上の休日」を与えなければならない。
●時間外手当
「法定労働時間」を超えた場合、「通常の賃金の1.25倍以上の賃金」を支給する必要がある。
●深夜手当
「22時から翌5時」までの間に働かせた場合、「通常の賃金の1.25倍以上の賃金」を支給する必要がある。
●休日手当
「法定休日」に働いた場合、「通常の賃金の1.35倍以上の賃金」を支給する必要がある。
※所定休日(法定休日を超える日数の休日)に働いた場合、必ずしも休日手当を支給する必要はない
●高校生などの労働時間
「22時から翌5時」の間は「満18歳未満」の高校生や学生などは原則として働いてはならない。
2. 時間外手当などが必要なケースとは?
「1日8時間勤務」「1週40時間勤務」のいずれかを超えた場合、「時間外手当」を支給する必要があります。
例えば、「1日7時間、週6日間」働いた場合、1日8時間は超えていませんが、週42時間労働となるので、「2時間分の時間外手当」が必要です。
法定休日は週1日ですので、週休2日制のいずれか1日を勤務させても「休日手当」を支払う必要はありません。
ただし、同時に「法定労働時間は週40時間」と定められています。40時間を超えた部分については「時間外手当」を支払う必要があります。
「22時から翌5時」までの深夜に勤務させたときは、別途「深夜手当」を支払う必要があります。
例えば、1日8時間を超えた法定時間外労働部分が22時以降の深夜労働の場合、50%以上の割増率となります{1時間当たりの賃金×1.50(1.25(法定時間外分)+0.25(深夜分))}。
まとめ