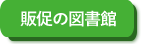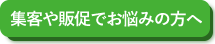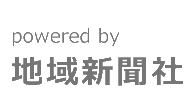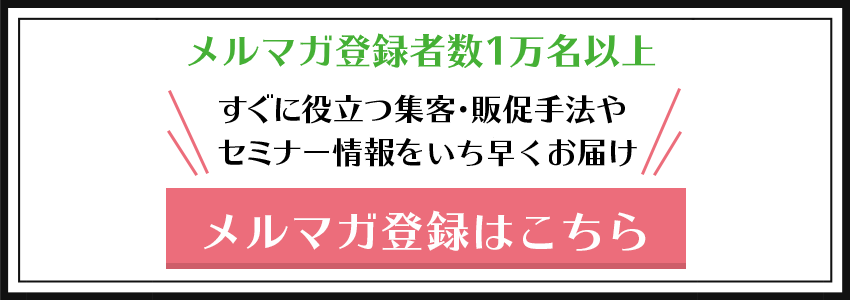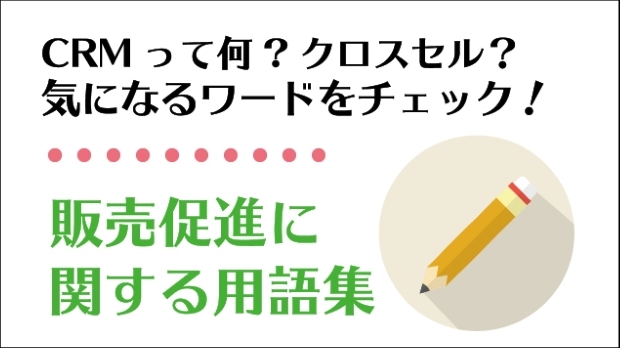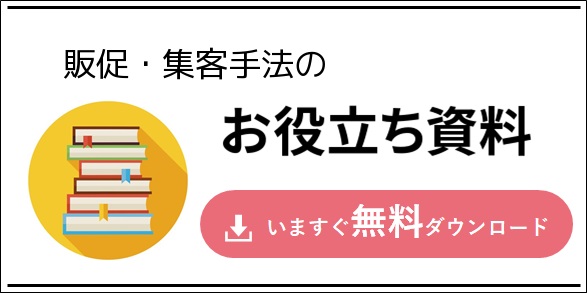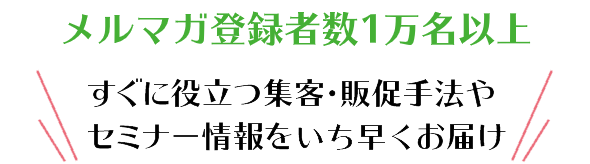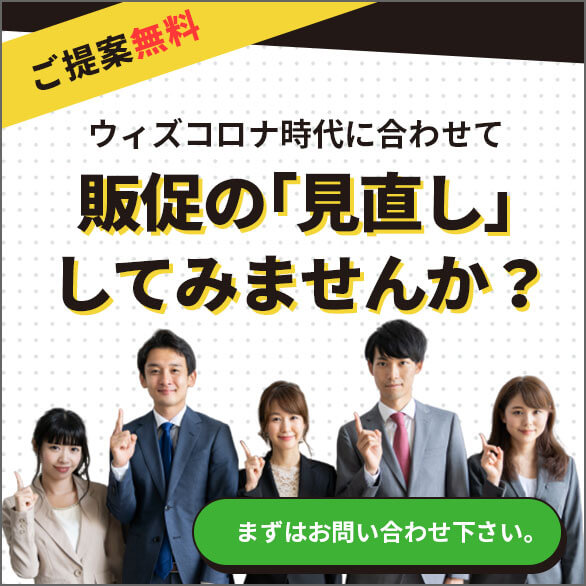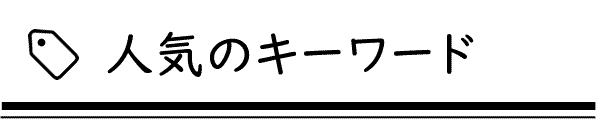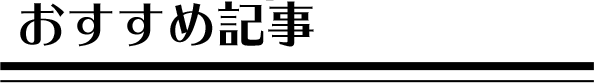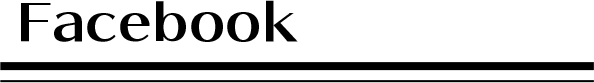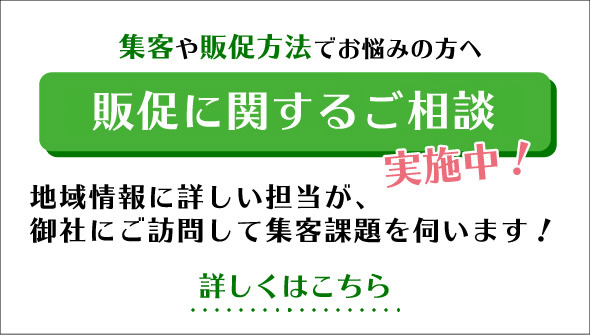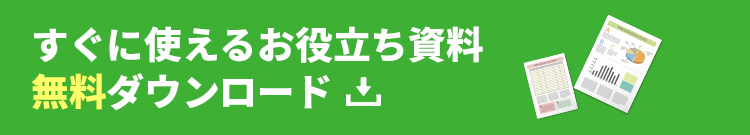景品表示法違反(優良誤認)とならないための広告表示の事例

前回は、広告表現において実際に行政処分(措置命令)を受けた法令違反事例のうち、二重価格表示に関するものをご紹介しました。
今回は、広告に掲載する商品の品質説明において、事実と反する記載となってしまい優良誤認表示とみなされた事例をご紹介します。
【目次】
1.実例をもとにした優良誤認表示のケース
2.景品表示法の広告表示の責任
1.実例をもとにした優良誤認表示のケース
広告主である某事業者が販売している食料品について、カタログ広告に
「素材の良さをいかしています。保存料・着色料・添加物・化学調味料など不使用」
「化学的な合成添加物は一切使っていません」
と記載していましたが、実際は、化学的な合成添加物で加工されたものであった。
として消費者庁は景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
景品表示法で不当表示として定められているもののうち、優良誤認とは、一言でいうと「誇大広告」のことであると解釈できます。広告主が、自己が販売・取引する商品・サービスにおいて、その品質や規格、その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客に訴求し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示が優良誤認表示とされ、禁止されています(景品表示法第5条第1号)。
商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽る
同業他社の商品・サービスよりも実態に反してとても優れているかのように偽る
そういった広告表示が優良誤認とみなされるわけで、これは一般的な認識における「誇大広告」のことだと認識すれば理解しやすいものと思います。
2.景品表示法の広告表示の責任
今回ご紹介した食料品の優良誤認の実例ですが、
従来、この食料品の仕入れ先メーカーは実際に合成添加物で加工せず広告主である某事業者に出していましたが、メーカーの品質管理ミスにより化学的な合成添加物で加工されてしまっていることが発覚、すぐに無添加にするよう切り替えた上で、某事業者は消費者庁にその旨を自主申告したという経緯があるようです。
いわば委託先メーカーのミスに起因するものであり、広告主が直接的に、故意に、不当表示を行ったと言えるものではありません。
しかし、優良誤認は広告主が「故意に」偽って広告表示する場合だけでなく、「誤って」広告表示してしまった場合であっても、あくまでその広告表示が優良誤認であると判断されれば、景品表示法による処分を受けることになります(無過失責任)。
つまり、委託先メーカーのミスであっても、広告表示責任のある(広告主である)某事業者が行政処分の対象となります。
いざ広告を出そうと思っても、内容やデザインは広告代理店や制作会社に一任してしまうということが、現実では多いと思います。また広告に掲載する商品・サービスについても、さまざまな委託先や代理店が実際の製造・販売を担っており、なかなかその実態を把握し切れないということも多いでしょう。
しかし、景品表示法において罰則を科される広告責任者は原則として広告主です。それをしっかりと踏まえた上で、誠実な広告マーケティングを実践していただければと思います。
まとめ